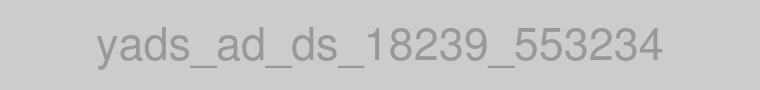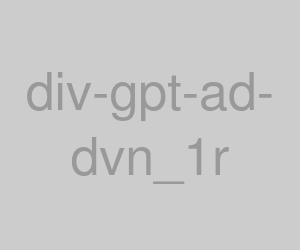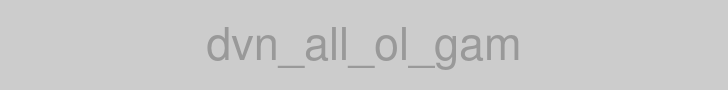上田泰己が解説する“睡眠”の新常識! 「体内時計」の仕組みは謎だらけ!?
PR 公開日:2024/6/22

かつて、ドキュメンタリー番組『情熱大陸』や『プロフェッショナル仕事の流儀』に出演、“科学界の若きプリンス”と称された睡眠研究者の上田泰己氏の著書『脳は眠りで大進化する』(上田泰己/文藝春秋)は、生活に欠かせない睡眠のメカニズムに迫る1冊である。かつての知識とは異なる「睡眠の新常識」は、どれも興味をそそられるものばかりだ。
■睡眠と「密接」に関わる体内時計のメカニズム
本書は「私たちはなぜ眠るのか」と問う。その仕組みを解明するにあたって、ふれているのが「体内時計」の存在だ。
体内時計は「ヒトに限らず地球上に生活するあらゆる生物」が有しているもので、「外部環境の変化に内部を合わせていくシステム」だと解説する。
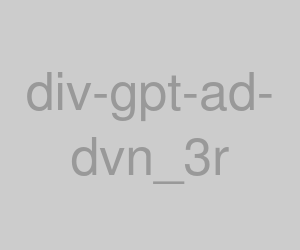
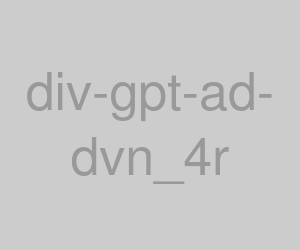
ユニークな事例として、スウェーデンの植物学者であるカール・フォン・リンネは、花が有する体内時計のシステムを利用して「午前6時から正午までに開く花、正午から午後6時までに開く花」を「1時間ごと」に並べた「リンネの花時計」を作った。

朝起きて、夜には眠くなる。これも体内時計によるもので、その存在を意識しやすいのは「睡眠の覚醒のリズムが崩れてしまった時」だという。例えば、1日だけの徹夜ならば、翌日にリズムは戻る。しかし、連日ともなると「別のモデル」が作られてしまい「入眠と起床の時間」が乱れてしまうのだ。
体内時計の研究は、古くから進められている。しかし、睡眠との「関係」は「密接」とされながら、その具体的な「機構」が明かされていないというのも興味深い。本書ではいずれ、睡眠の仕組みがより解明されれば、体内時計の「機構図が浮かび上がってくる」と期待を寄せる。
■子どもたちの眠りを分析する新たな取り組み「子ども睡眠検診プロジェクト」
日本が、全世代にわたって「睡眠時間が非常に短い国として知られている」とは驚きだ。本書では、質のよい睡眠を手に入れるための「睡眠衛生」に言及し、ひいては、睡眠不足による「経済損失」の可能性も指摘する。
その流れを受けて、近年では「健康な睡眠」を得るための取り組みが進められている。なかでも、本書で興味をそそられたのが「睡眠医療」だった。
本書によると、睡眠医療には「睡眠時の障害となる疾患を改善する目的」がある。しかし、かねてより患者と接する「臨床」が行われ、睡眠に関する「器具や製品」もあったものの、病気を未然に防ぐ「予防」へのアプローチが「手薄」だったという。
一つ、実際に動き出したのが2022年スタートの「子ども睡眠検診プロジェクト」だ。学校単位で申し込んだ「小・中・高等学校」に向けてウェアラブルデバイスを送り、取得された子どもたちの睡眠データを、プロジェクトを進める東京大学のシステムズ薬理学教室が「パーソナルレポート」として分析結果をフィードバックする。
いずれ、国民的な「睡眠検診」で「あなたの1週間の睡眠時間の平均はこれぐらいで、睡眠の質はこれくらいです」と伝えられるのが「理想」と、著者は願う。「健康な睡眠」の基準が提案される日が来れば、私たちも安心できそうだ。
本書はよくある“睡眠マニュアル”ではなく、睡眠に関する興味深い研究結果も多数収録している。寝る間も惜しんで読みふけてしまうほどの面白さではあるが、ほどほどに楽しんでいただきたい。
文=カネコシュウヘイ