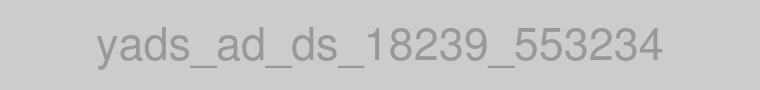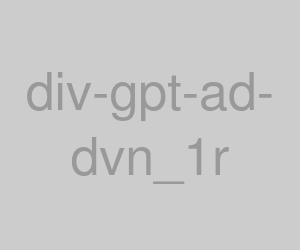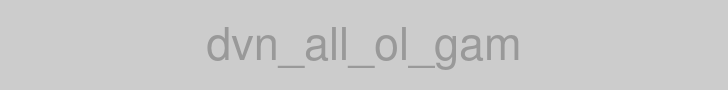もしも道端で「塗り壁」に出会ってしまったら… 棒で足をくすぐると消える!? 親子で楽しめる『伝説の化けもの図鑑』
PR 公開日:2024/7/20

危険な暑さが続く日々。外で遊ぶのも難しく、時間の過ごし方を迷うことも多いのではないでしょうか? そこで親子一緒に楽しめる一冊として紹介したいのが、『伝説の化けもの図鑑』(山北篤:監修、池田明久実:イラスト/中央公論新社) です。映画化もされた「おばけずかん」シリーズや、妖怪ウォッチなど、おばけ・妖怪は子どもに人気のある存在。そんなおばけ・妖怪から精霊まで、世界各地に伝わる化け物たちを紹介するのが本書です。
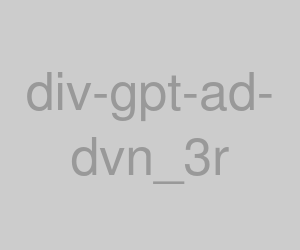
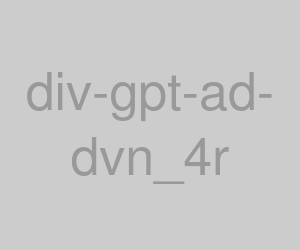

我が家は小学2年生、5歳の男の子がふたり。小2はひとりで、5歳は私と一緒に読むことにしました。
“図鑑”というだけあって、100種類以上の化け物が登場。それぞれの出没地や特徴、誕生の経緯などが説明されます。5歳次男はそもそもおばけなどが苦手。すぐに読むのをやめてしまうかと思いきや、意外と楽しんで最後まで読み終えました。それはきっと挿絵のおかげ。どの化け物も怖さがあるものの、ポーズや表情がどことなくかわいく、ユーモアもあります。

ページをめくり、気になるところを見つけては「ここ読んで」と要求。特に「ぬりかべに出会ったら棒で足元をくすぐると消える」など撃退法に対して「夜は傘持って歩かないとね!」と真剣にリアクションする姿が我が子ながらかわいい……! こちらも読み聞かせながら幸せをもらえました。
一方、読書大好き長男は真剣に熟読。知らなかった化け物たちに大興奮でした。特に興味を持ったのは、メドゥーサ・アルゴスなどギリシャ神話に出てくる怪物たち。ギリシャ神話自体を知らなかった長男ですが、いろんな神様と怪物が出てきて戦って……小学生男子とギリシャ神話、親和性が高いことに気づきました。

ふたりとも大喜びだったのがドラゴン大解剖&世界のドラゴン大集合のページ。かっこいいドラゴンたちにくぎ付けになっていました。


ふたりが寝た後私も改めて読んでみたのですが、大人からしてもかなり読みごたえあり!
例えば先述のドラゴンのページでは、一口でドラゴンと言ってもその意味合いは各地の歴史や宗教観によって様々であることも説明されています。中国では龍=ドラゴン、神聖な霊獣とされていましたが、キリスト教では反対に神様の敵であると考えられていたそうです。似たような怪物をイメージしていても、その意味は正反対なところが面白いなと感じました。
また日本のおばけ・妖怪は「川には河童がいる」「地震が大鯰(おおなまず)の仕業」など、命を守るためだったり、原因不明の恐怖に理由を求めた結果だったりと何かしら意味を持って生まれてきたイメージがありました。しかし豆腐小僧、ケラケラ女などキャラクター的な人気があるものもいて、江戸時代の雑誌などで人気を集めていたというのには驚き。

世界の化け物たちを知るにつけ、各国の文化や宗教などの背景がわかればもっと面白いんだろうなと感じ、久々に親の知識欲も刺激された一冊でした。
文=原智香