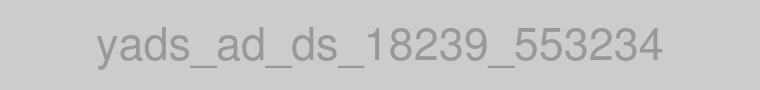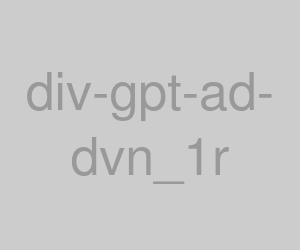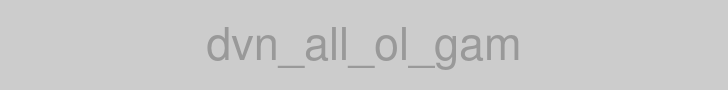お歳暮を贈る時期は? うっかり贈りそびれたらどうする?【お歳暮のマナー】/お正月のしきたり・マナー
公開日:2024/12/7

日頃からお世話になっている方に、感謝の気持ちを込めて贈る「お歳暮」。目上の方や上司、恩師に贈るものだからこそ、失礼のないようにしたいものです。うっかり贈りそびれてしまった時や喪中の場合など、どんなことに気をつけたらいいのでしょうか。「大人の品格マナー」の講師である末永貴美子さんに【お歳暮のマナー】を聞きました。
お歳暮を贈る時期は?
お歳暮は、1年の締めくくりに贈るもの。そのため、年の瀬が近づいた12月初旬から12月20日頃までに贈るのが一般的です。11月頃からデパートなどで売り出されますので、早めに準備をしておけるといいですね。
12月20日までに贈れなかった場合は?
年末に差しかかると、相手もお正月の準備などで慌ただしくなるものです。12月20日をすぎてしまった場合は、無理に贈るのではなく、年が明けてから「お年賀」を贈るのがおすすめです。お年賀とは、年始のご挨拶として贈る品物のこと。のし紙には「御年賀」「御年始」「賀正」などの文字を記します。
喪中の時はどうしたらいい?
お歳暮は祝いごとではなく、日頃の感謝を込めて贈るものですから、自分や相手が喪中の場合に贈ってもいいといわれています。
注意したいのは、お歳暮が間に合わず、お年賀になってしまう場合です。喪中はお年賀を贈れませんので、その代わりに「寒中見舞い」を贈りましょう。寒中見舞いは、松の内(一般的に元日から1月7日まで。関西では1月15日頃まで)が終わってから立春(節分の翌日)までにお贈りできるといいですね。
お歳暮の相場や、品物を選ぶ時の注意点は?
昨今、お歳暮の相場は5000円前後といわれています。相手の好みが分かる場合は、好みに合わせた品物を贈るのが理想的です。
もし、牡蠣やカニなどの魚介・海鮮を贈る場合は、要注意。相手が留守の間に届いてしまうと、迷惑をかけることがあります。事前に届くタイミングを伝えておくと良いでしょう。
お歳暮をいただいた場合の対応は?
お歳暮をもらったら、できるだけ早急にお礼状を書きましょう。お礼状には、時候の挨拶や、お相手の近況をたずねる言葉のほか、お歳暮をいただいたお礼を必ず書き添えます。
お歳暮は基本的に、お世話になっている方が、お世話してくださっている方に贈るもの。本来、一方通行で贈るものですので、品物のお返しをする必要はありません。昨今は友だち同士でお歳暮を贈り合うこともあるようですが、あまり多くないケースです
正しい“のし”の掛け方は?
お歳暮の“のし”は、右側の紙が上になるように掛けるのが正しい方法です。箱を裏返し、右から開けられるように、右を上にします。左側が上になるとお葬式の掛け方になってしまうので、注意しましょう。
なお、お店などで「のしはどうされますか?」と聞かれることがあると思いますが、のしは基本的につけるものと覚えておきましょう。デパートなどから贈る場合は、配送伝票を貼るために、品物の箱に直接のし紙を掛け、その上から包装紙で包む「内のし」が一般的。手渡しの場合は「外のし」が多いようです。
お歳暮を失礼なくやめる方法は?
「縁が切れたら贈らないで良い」とされるお歳暮ですが、突然やめてしまうのは失礼なのでは…と考える人も少なくないようです。
突然やめるのが気になる場合や、「今年はお歳暮がないけど大丈夫かな?」と心配されるような間柄であれば、手紙でお知らせするのがおすすめです。お歳暮の添え状に「今年で最後にさせていただきます」と記してもいいですし、年賀状のような形で伝えるのもいいでしょう。お互いに良い印象を保つための丁寧な方法といえます。
相手が両親や兄弟など気の知れた間柄の場合は、「来年からなしにさせてもらってもいいですか?」と本音でお話をしてもいいのではないでしょうか。
また、お歳暮は1年の総括になりますので、お中元とお歳暮の両方を贈っている場合は、まずお中元をやめ、お歳暮を3年くらい贈ってから徐々にフェイドアウトする、という方法もあります。
手渡しする際のタイミングと挨拶は?
手渡しをする場合でも、贈る時期に違いはありません。「本年もお世話になりました」という挨拶を添え、品物を贈りましょう。
本来、お歳暮は手渡しするのが最も格式高いといわれていますが、昨今は配送することが増えてきました。相手との関係性によっては、手渡しにしたほうがいいケースもあります。
目上の方々との良い関係を保つためにも、大切に贈りたいお歳暮。失礼のないように準備をして、1年を気持ち良く終えられるといいですね。
取材・文=吉田あき
<第2回に続く>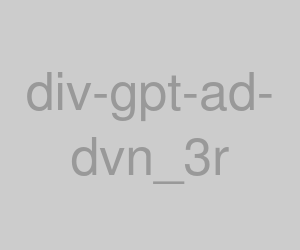
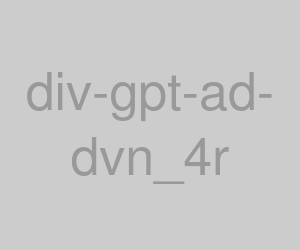

末永貴美子(すえながきみこ) 日本庭園を有する800坪の屋敷で、実業家の祖父と茶道家の祖母の影響を受けて育つ。日本の文化や文学に興味を持ち、着物についても深く学ぶ。一般企業に勤めたのち、心理学やパートナーシップ、美容などさまざまな分野を学び、多くの人と出会う中で内側からにじみ出る品格、美しさを一生かけて追求したいと考えるようになり、品格のある女性になるためのマナースクール「美礼塾」を立ち上げる。テーブルマナーを中心に発信するInstagramやLINEセミナーも人気。著書は『ふだんのふるまい帖 ふつうに生きているだけで、一目置かれるひとになる』(KADOKAWA)。 Instagram:@kimiko.suenaga