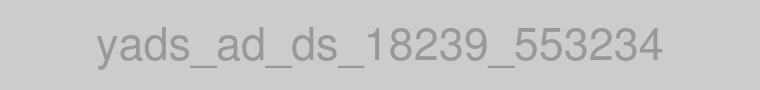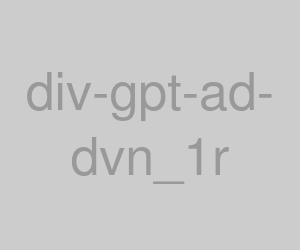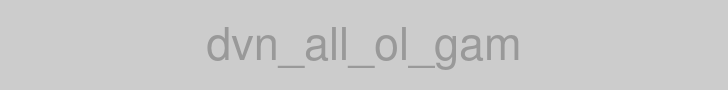「誰が最後に『本』を救うのか?」―出版社の元社員がリアルに描く出版業界の裏側とは? 藤脇邦夫著『断裁処分』
更新日:2017/11/12

ダ・ヴィンチニュースでは以前、永江朗さんによるノンフィクション『小さな出版社のつくり方』(猿江商會)について取り上げている。
「この本の良さをわかる人だけわかってくれればいい」の思いがあれば、企画から発行まですべて1人でこなすことができる。創業資金も「いい車を1台買える予算があれば、なんとかやっていける」し、資金が不安ならクラウドファンディングを募ったり、兼業したりしながら続けてもいい。情熱と軽いフットワークで自分が読みたい本を作れる“小さな出版社”から、目が離せない……。こんな内容のインタビュー記事だった。
小さな出版社が元気な一方で、小説などを発行してきた老舗出版社は現在、どうしているのか。ラノベやマンガのライツ(版権)事業でウハウハなところもあるようだけど、二次元創作媒体がなくそれこそ文学や人文・社会科学系がメインの、高尚ながらもお堅い本ばかりのところは何を屋台骨にしているのか。
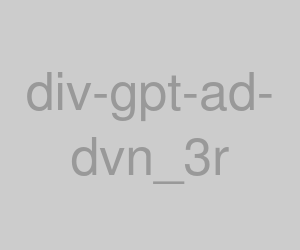
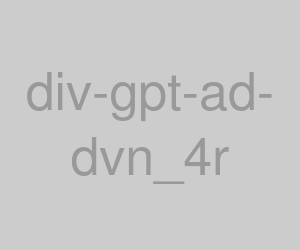
藤脇邦夫さんの小説『断裁処分』(ブックマン社)は、フィクションながらもその問いの答えに触れている。
すぐれた文芸書を多くの人に届けてきた老舗出版社の新英社は、深刻な経営危機に陥っていた。創立約100年、知らない者はいない有名出版社だったが、マンガと若者向けの雑誌がなく最近では古いイメージしかなかった。それでも文庫は堅調な売り上げをキープしていたものの、ここ10年の出版不況で倒産寸前に陥っていた。
一方、日本の出版社最大手のひとつ集談社も、安泰とは言い難い状態だった。純文学雑誌『文芸界』主催の『文芸界賞』は芥木賞と直川賞(!)への早道と言われているが、『文芸界』の社内での扱いは低く、いつ廃刊になってもおかしくない状態だった。
理由はひとえに、文学作品が売れないから。『文芸界賞』を取った本でも最近は1万部も売れない。そのくせ小説家の多くが気位ばかり高く、編集者にタダ飯をおごってもらうことに余念がない。だから「そんな無駄なことに費やす経費はない。編集長を続けたいなら広告代理店と組んで、100万部売れるヒット作を生み出せ」と『文芸界』編集長の門脇に向かって、編集総務 担当常務の通称“役員”はばっさり言い放つ。つまりマンガや若者にウケるコンテンツがない会社は屋台骨などなく、もはや崩れ落ちる寸前なのだ。
「マンガやラノベは子供向けの暇つぶしで、文学こそが人々の心を豊かにするもの。本を読まないとバカになる」。このような言説は今の時代にも生きているけれど、そう言って子供からマンガを取り上げてきたはずの大人も、もはや文学を手に取らない。リアルの世界でもそれは同じだ。だから誇張はあるものの、大手出版社が置かれた状況はこの本の世界と、実はそう違わぬかもしれないと思ってしまう。
聞くところによると藤脇さんは、実用本を多数扱ってきた出版社の元社員だったそうだ。
だからなのか想像の産物だとわかっているはずなのに、ノンフィクションを読んでいる錯覚に陥ってしまう。同書に出てくる出版社や印刷会社、取次などの会社名は架空のものだが、書店や出版に少し詳しい人なら「これはあそこがモデルだな」と、すぐわかるかもしれない。そして大御所ながらも最近は新作を書けていない作家たちによる文学賞選考バトルロワイヤルのシーンでは、「この作家は〇〇氏だろうか?」と、楽しくも下卑た想像をしてしまうことだろう。
新英社はその後、出版業界の色々な思惑に振り回されることになる。大事に守り続けていた作家たちの版権が破格の安価で取引されそうになるものの、最後の最後に新英社も読み手も、あるギフトを受け取ることができる。同書の帯にも「誰が最後に『本』を救うのか?」と書かれているが、それはぜひ自身で確かめてほしい。そして幻冬舎代表取締役社長の見城徹氏が「出版業界を志望する人は読まないで下さい」との言葉も寄せているが、むしろ出版業界を志す人こそ、積極的に手に取ってほしいと思う。厳しい現実を突き付けられながらも、まだギリギリ「出版業界、こうだったらいいよね」を形にできる人たちが存在していることがわかるからだ。
文=今井順梨