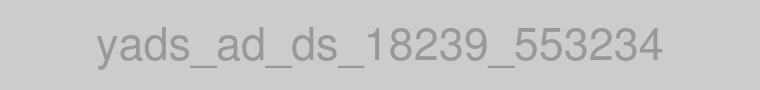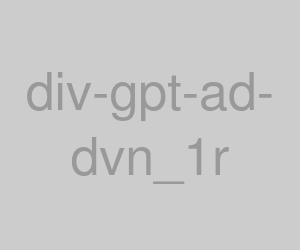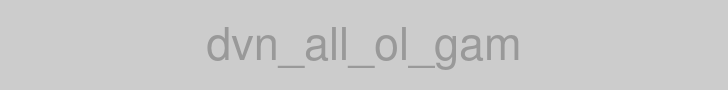部下の行動を成果につなげる! 新しいコミュニケーション習慣「1分ミーティング」
公開日:2019/6/5

「人手が足りない」。これはどの企業でも頭を悩ませる課題です。「生産性を上げよう」「離職率を下げよう」。これもどの企業でも掲げられている標語です。しかし、そのための対策会議やミーティングを重ねるばかりで仕事が進まず残業続き、人材育成に割く時間も少なくなり、耐えきれずに部下が辞めていく。こうした事例に思い当たる人もいるのではないでしょうか。
「長くても1分」。行動科学マネジメントを研究する石田淳さんは、自身の著書『仕事も部下の成長スピードも速くなる 1分ミーティング』(石田淳/すばる舎)で、行動科学に基づく時短ミーティングを提案しています。
行動科学マネジメントとは、「成果を出す優秀な人間は、成果を出す行動を取っている」と捉え、その行動を分析して誰でも再現可能なルーティーンに落とし込む手法です。
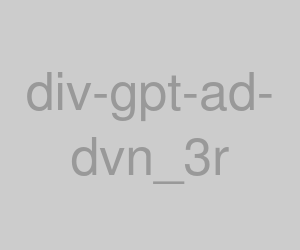
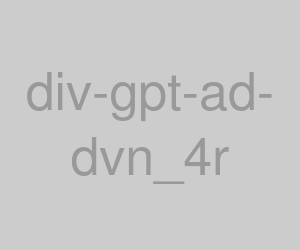
「1分ミーティング」は、1分間の短い対話で部下の行動を分析することで、自発的によい行動を起こさせ成長を促し、部下との信頼関係を築けるといいます。その最大の利点は、文字通り超時短であることです。忙しいなかで自分と部下に負担が少ないというのは何よりもメリットに感じます。
■コミュニケーションを時間と回数で管理する
その方法も実にシンプルです。場所も時間帯も問いません。朝一番の始業前に部下のデスクに向かい、「○○君、おはよう。今日は何をするの?」と声をかけるだけです。
ポイントは、相手と1対1で話すこと、部下の全員と行うこと、毎日1回を目標に行うことです。
そんなことかと思ってしまいますが、これができない上司ばかりなのが現実であると訴えます。
社会人には「部下が上司のところへ報告にいくもの」という暗黙の了解があり、それが部下の「報連相」のハードルを上げているとしています。まずは上の者から歩み寄り、心理的な距離を近づけることが大事です。だから毎日の習慣にすべきなのです。
そして上から目線のコミュニケーションは自己満足になりがちです。付き合いやすい部下とだけ話して満足していると、職場の人間関係に偏りが生まれてしまいます。均等に対話するためには、誰とどれだけ話したかを時間と回数で把握することが重要です。
■成果につながる行動を促す
会話の中で確認するのは、部下の行動です。評価するのは「成果につながる行動」かどうか。相手の人間性を評価することが悪いわけではありませんが、内面に踏み込まれるのを嫌がる人もいます。これは叱る場合も同様で、注意すべきは行動なのに内面を否定しているケースが多いのです。
また「それはやらないくていい」「それはダメだ」と行動を否定すると、かえってその行動が増えてしまうとか。悪い行動を止めさせるには、相槌を打たないこと。これを行動科学では「行動の消去」と呼び、否定よりも無反応で流してしまうのが最も効果的だといいます。
行動科学マネジメントでは、心構えや精神論による働きかけを禁じています。変えるべきは行動であり、内面ではないのです。例えばセミナーや勉強会を行って、仕事を好きになったり、モチベーションが上がったりしても、それが成果につながる行動に直結しなければ意味がないからです。
部下の行動を変える前に、まずは上司や先輩の行動から改める必要があるようです。
文=愛咲優詩