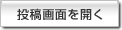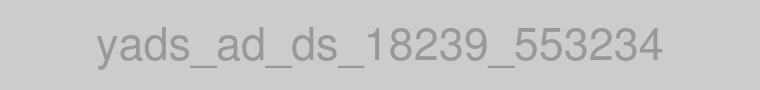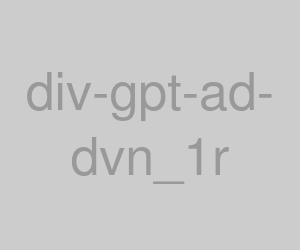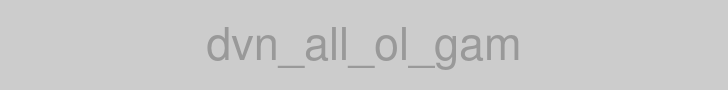「今月のプラチナ本」は、岸政彦『図書室』
更新日:2019/8/6
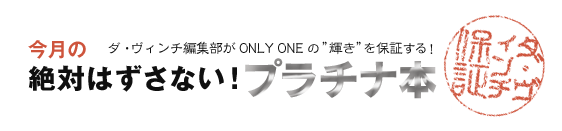
あまたある新刊の中から、ダ・ヴィンチ編集部が厳選に厳選を重ねた一冊をご紹介!
誰が読んでも心にひびくであろう、高クオリティ作を見つけていくこのコーナー。
さあ、ONLY ONEの“輝き”を放つ、今月のプラチナ本は?
『図書室』
●あらすじ●
大阪の古い団地でひとり暮らしをしている50歳の「私」。定職も貯金もあり、生活に不満はない。けれど最近、子どもの頃のことばかり思い出してしまう。猫たちとの暮らし、帰りが遅い母親を待つ夜、そして、いつも通っていたあの古い公民館の小さな図書室――。ひとりの女性の追憶を描いた表題作「図書室」に、著者が同じ大阪での人生を綴る書き下ろしエッセイ「給水塔」も併録。
きし・まさひこ●1967年生まれ。社会学者。主な研究テーマは沖縄、生活史、社会調査方法論。『断片的なものの社会学』で紀伊國屋じんぶん大賞2016受賞、17年『ビニール傘』で第156回芥川賞候補、第30回三島賞の候補に選出される。その他の著書に『はじめての沖縄』『マンゴーと手榴弾―生活史の理論』など。
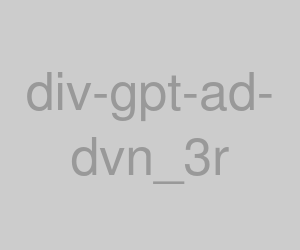
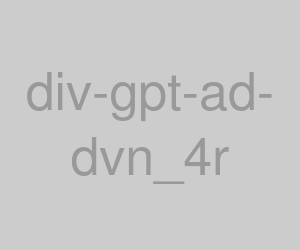
編集部寸評
生きるためのよすがは、自分の中にある
本書は小説とエッセイを1本ずつ収めるが、小説では主人公「私」が、エッセイでは著者が、それぞれの追憶にふける。脳裏に映るのは、些細な断片だ。淀川の岸辺の小屋、台風直後の海、大学をさぼって行った万博公園。著者はこう書く。「暗い穴の底のようなところで暮らしていても、偶然が重なって、なにか自分というものが圧倒的に肯定される瞬間が来る。私はそれが誰にでもあると信じている」。それがあれば生きていける。そんな記憶が自分の中にもあることを、本書は教えてくれる。
関口靖彦 本誌編集長。『小説 天気の子』の編集を担当しました。ラストの一言は、誰もがいま必要としている言葉だと思います。映画と、本誌特集と共にぜひ!
忘れていた子どもの頃の記憶が顔を出す
気に入った本を何度も読み返すのが好きで、新しい本になかなか手が出せない。しぶしぶ読んでいると、気づいたら新しい冒険に夢中になっている。ああ〜、子どもの頃ってそうだったなぁと思う。そして「私たちはもう十歳かそこらで、男というものに絶望していたような気がする」という一文が出てきたときに思わず笑ってしまった。そこに至る過程が、多くの女性が記憶しているであろう小学生男子へのいらだちを的確に表現していたから。「図書室」は、穏やかな記憶の断片だった。
鎌野静華 ベランダにあるオリーブの木。今年はじめて花が咲きました。おおっと思っていたら隣のローズマリーもはじめての花が。なんだろう、いい季節だ。
怖いけど気になる街、大阪が生んだ本
大阪を歩いていると、圧倒的に他人を感じる。匂いも色もソースっぽい街並みは主張が強くて怖いが、眺めていると安心する。そこで暮らす岸さんの文章が好きなのは、徹底して他人でいてくれるからなのだと本書を読んで思った。「図書室」の主人公・美穂の語りと彼女を通り過ぎていった人々の描写は、決してブレることのない“視点”を感じさせ、つい身を委ねたくなる。気づけば彼らと一緒にどこかへ運ばれてしまう。その原点が垣間見える「給水塔」も必読で、後を引く一冊だ。
川戸崇央 『図書室』は川上未映子さんの帯文も含めて本当に素晴らしい本だった。東北出身の私にとって大阪は遠い存在だが、また意味もなく散歩しに行きたい。
偶然が重なり肯定される瞬間、絶対ある
大阪の女子高に通学していた頃、梅田まで電車から淀川を見て、梅田から最寄り駅までまたも淀川を眺める毎日を送っていた。表題作の「図書室」に強烈な懐かしさと、そして記憶の尊さを想う。「給水塔」の〈偶然が重なって、なにか自分というものが圧倒的に肯定される瞬間が来る〉の一文がまたたまらない。「何回この川渡るねん」と通ったあの学校で私は肯定されたし、今住む場所にもそれがある。偶然のそんな瞬間を信じるし、私にはあの日の記憶があるから大丈夫と思えた大切な一冊。
村井有紀子 『図書室』すべてが懐かしかったです……! そして今月号は星野源さん表紙&エッセイ「いのちの車窓から」も3カ月に一度の再開になります!
もう会わないあの人、元気ならいいな
人生のある時期とても近いところにいて、でも何かの理由で、あるいは理由もなく会わなくなってそれきり。読んでいるといつのまにかそんな人の顔が浮かんでくる不思議な小説だ。語り手の美穂が淀川を眺めながら思い出す、10年一緒に暮らした男、図書室の少年、彼と拾った猫、その誰もいまは彼女のとなりにいない。それでも記憶の中で再生される会話、彼らと一緒に見た景色があまりにきれいで苦しくなる。今はもうない、でもかつて確かにあった光、その美しさを思い出させてくれる物語。
西條弓子 かつて近しくて今はもう会わない人を、川を見ながら思い出してみたいものですが、私は確実に検索する。この世にインターネットがある限り‼
私らだけの図書室
人類が滅亡して自分たちだけが生き残ったら。突拍子もないことを真剣に考える、小学生時代の彼女とある男の子との回想を追ううちに、自分の子どものころを思い出す。人の話を聞きながら記憶が呼び起こされて、「私もさ〜」と話したくなるあの感じ。それほど交わされる会話がリアルなのだ。物語としては、最後にちらりと出てくる彼女の家族にまつわる話のほうが、きっと起伏があって派手だ。けれどその奥に眠る思い出を共有したからこそ、彼女そのものに触れられたような気がした。
三村遼子 小学生のときに友達と回していた交換ノート。具体的な内容はまったく思い出せないけれど、当時の自分にとってものすごい秘密を書いていたはず。
気持ち良く、記憶の波にたゆたう
表題作「図書室」の読後、幸福感に満たされた。語り手の「私」と違って、わたしが思い出す幼い頃の記憶はいつも恥ずかしいものばかりなのに、少年と交わす大阪弁や描写の追憶を読んでいくうちに、忘れていたなんでもないが幸せだった記憶がよみがえる。気づけば、わたしと「私」の境界線があいまいになり、今感じている幸福感が誰のものかわからなくなった。読み進めるにつれ、読み手のパーソナリティがうすれていくような不思議な感覚は、怖くはなく心地よい。唯一無二の作風。
有田奈央 作中にある缶詰を食べるシーンで、自宅にある非常食の賞味期限がそろそろなことに気づく。今の非常食っておいしいんですね。アルファ米すごい。
“あの頃”の自分に出会う
本書を読み終わったとき、ふと過去へと思いを馳せている自分に気づいた。本書はある女性の追憶の物語と著者の自伝エッセイで構成されている。著者によって記される言葉は温かくて優しいのに、どこか切ない。それは本書を通して感じる「懐かしさ」の正体が「過去になった現実」であるからだろうか。何気ない日々、切り取られた日常の一瞬が、次の瞬間には過去になっていく。自分という存在さえもひどく曖昧な世界だからこそ、そこに在った“あの頃”の自分が愛おしくなる一冊。
前田 萌 編集部に配属された新人です!公式Twitterの担当になりました。様々な情報をお届けできるよう頑張ります。コメントいただけると嬉しいです!
読者の声
連載に関しての御意見、書評を投稿いただけます。
投稿される場合は、弊社のプライバシーポリシーをご確認いただき、
同意のうえ、お問い合わせフォームにてお送りください。
プライバシーポリシーの確認