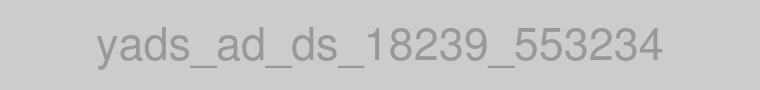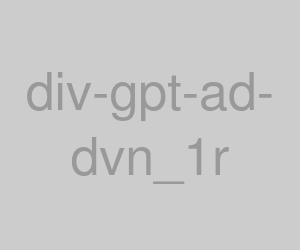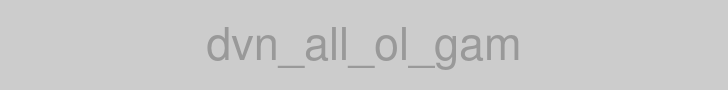言葉を文字通り受け取ってしまう、嘘がつけない…「普通」であれないことに悩む“非定型発達”とは
公開日:2020/12/30

なんで自分は、普通のことが普通にできないんだろう…。これまでの人生の中で、そう感じたことがある人は意外に多いはず。他の人ならなんなくこなせることが上手くできなかったり、周りから「空気が読めない」と言われてしまったりすると、自分という人間に「ダメ」という烙印を押されているような気がしてくる。
そんな苦しさを抱えながらも普通であるよう頑張っている人に、ぜひ読んでほしいのが『空気が読めなくても それでいい。: 非定型発達のトリセツ』(創元社)。
本作は、ベスト&ロングセラー『それでいい。』シリーズの第4弾。本シリーズでは、『ツレがうつになりまして。』(幻冬舎)を手掛けた漫画家の細川貂々さんと、精神科医で対人関係療法の第一人者である水島広子先生がタッグを組み、生きづらさ解消のヒントを伝授。
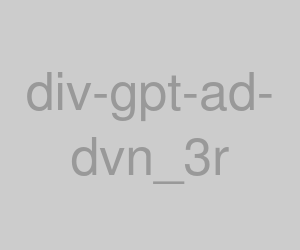
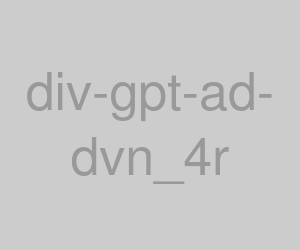
今回のテーマは、非定型発達。いわゆる、病名のつく「発達障害」ではないが、日常のさまざまな場面で生きづらさを抱える、「グレーゾーン」と呼ばれる非定型発達の特徴や付き合い方を解説している。
「非定型発達」という生きづらさを解消するには?
世の中の大半の人は「定型」。損得勘定で動いたり、言葉から裏に込められた真意を汲み取ったりすることができる。だが、非定型発達の人たち(非定型)は違う。嘘がつけなかったり、裏表がなかったりと、定型とは異なる特徴を持っている。
非定型とは、脳の発達の仕方に偏りがあり、さまざまな生きづらさに繋がる特徴がある先天的な変異のこと。社会適応の難しさからさまざまな病気を発症し、長引くケースも多いという。
実は、作者の細川さんも非定型。非定型には主に2つのタイプがあるのだが、本作で水島先生は発達障害の名前を援用し「ASD(自閉症スペクトラム症)タイプ」と「ADHD(注意欠如・多動症)タイプ」に分類し、細川さんのASDタイプを中心に特徴を説明している。
たとえば、細川さんは空気を読むことが苦手で、本音と建前が分からない。言葉を文字通りに受け取ってしまうため、中学時代には友人から「足が太いでしょう?」と聞かれた時に素直に認め、怒られたことも。他にも、グループに入っていけない、マルチタスクが苦手などといった悩みも抱えている。
非定型は悪気があるわけではないが、持っている特徴によって誤解が生じ、人間関係で苦しんでしまうことも少なくない。そこで水島先生は、そんな生きづらさを解消するヒントを教えてくれる。
中でも、特に印象的だったのが定型の人に向け、非定型の側が自分の取扱説明書を作るという解決法。その際は「迷惑をかけます」「お世話になります」という気持ちを持つと、誤解されにくくなるという。
また、「解説者を作る」という方法もおすすめ。実際、細川さんもパートナーであるツレさんや友人が、自分の読めない部分を読んでくれたり、苦手なことをやってくれたりするので、助かっているそう。
こうした存在を身近で見つけることは生きづらさを解消するだけでなく、人生の質を高めることにも繋がっていく。非定型の人はぜひ参考にしつつ、今よりもありのままに生きやすい環境を築いてみてほしい。
「定型でもいいし、非定型でもいい」と言える社会に
自分が非定型であるかどうかを知るのは、勇気がいる。だが、一歩踏み出してみると、社会の見え方が変わるかもしれない。
細川さんもはじめは診断結果を知り、パニックになったが、次第に考え方が変わっていった。そして、水島先生から非定型について学んだ後は、いつもの景色が金色に輝いて見えたそう。
“私もう ムリにフツーにしようとしなくていいんだ 「私このままでいいんだって!!」 道ですれちがった人に言いたいくらいウキウキしました”(引用)
そして、本書を作る過程では「自分という人間はこういうもの」と把握し、インストールできたという。以前よりも生きることが楽になった細川さんは今後、同じように生きづらさを感じている人たちの役に立てるような生き方をしたいとも考えてもいる。
定型でもいいし、非定型でもいい――。そうお互いに認め合える社会を作るには、自分という人間を知ることと、違う特徴を持った人が身近にいるかもしれないと考えることの両方が大切。そのことに気づかせてくれる本書は非定型の人だけでなく、定型の人にとっても価値のある1冊だ。
文=古川諭香