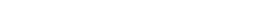濹東(ぼくとう)綺譚 (岩波文庫)
濹東(ぼくとう)綺譚 (岩波文庫) / 感想・レビュー
ヴェネツィア
荷風は初めてだが、概ね想像通りの文体、内容だった。私小説風の語りだが、作家はしきりにそう思われることを避けようとしている風だ。小説内小説『失踪』を設定しているのもそのためだろう。小説は、「わたくし」の一人称で語られるが、その語り手は、あくまでも大江匡だ。ただ、作中の彼は58歳の小説家であり、これを書いていた時の荷風にそのまま重なるのである。小説は、戦前の墨東はこんなだっただろうかと想像され、そこに流れる時間はきわめてゆったりとしている。作家にとってのアジールであり、失われたものへの郷愁だったのだろう。
2014/05/05
康功
私娼の女性との淡い恋心。墨田川を挟んで、開発された銀座、浅草の今と、昔の風情が残る墨東、玉の井地区の対比から、荷風の理想の女性をお雪に写し出す。半自伝的小説であり、沢山の実在する場所があることから、荷風の暮らしぶりが伺える美しい作品だった。映画化もされたらしいが、やはり原作がいい。
2016/11/21
カブトムシ
岩波書店版(昭和12年<1937年>)老作者<わたくし>(大江匡<ただす>)は「失踪」という小説の腹案をもって、浅草から玉の井あたりを散策している。ある日、夕立に出会い、たまたま髪結いから出て来た玉の井の女お雪を傘に入れてやるという奇縁が生じる。作中に別の小説の筋を入れた方法上の新しさをもち、一方で随筆の味わいも感じさせる。彼の身分を知らぬお雪が真剣な愛情を感じているのに気づくと、彼はそのまま遠ざかるという筋を時代の風俗と四季の推移の描写をまじえて、随筆ふうに展開する。昭和初期の荷風復活を決定づけた名作。
2020/09/04
ベイス
断腸亭日乗に、偶然出会った街娼と関係をもつことを、「女の身上を探聞し小説の種にして稿料を貪らんとするわが心底こそ売春の行為よりもかえって浅ましき限りと言ふ」と記している。この小説のハイライトであるお雪との別れの背後にも、荷風の後ろめたさが垣間見える。文壇からも家族からも国家からも自由だった荷風。生涯にわたり、浅草などを遊び歩いたが、そこには、小説の材料を集めるといういくらかの「打算」があったのかもしれない。そしてそのことを気にしていたあたり、ますますこのおっさん(失礼)が愛おしくなる。
2020/09/06
てら
改めて面白いなと思ったのはむしろあとがきにあたる「作後贅言」。明治の、特に関東大震災前にあった日本・東京の美風が急速に失われているのを肌で感じている荷風のグチが興味深い。『断腸亭日乗』と合わせて考えると、近代日本の恥部・暗部みたいなものまで浮かび上がってくるから困る。
2009/09/23
感想・レビューをもっと見る