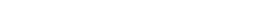燃える家
燃える家 / 感想・レビュー
けい
田中慎弥さん初読み。芥川賞作家だけに構えて読みだしたが、意外に読みやすい文章ですんなり頭の中でイメージが作れる物語。ただ本作(田中さんの作品は他作品も同様かもしれないが)の内容がかなりハード。いわゆる父殺し(父系へのコンプレックス)を話の骨格として据え、様々な要素を盛り込み展開されるが、読む側が追い込まれてくるので思わず休憩を挟みながら読むはめに。内容・文章ともに面白かったが、読後の疲労感は格別大きい。疲れたー。
2014/01/03
優希
強烈な匂いを放つ作品でした。生きる者と死する者、血生臭さ、命といったイメージが強烈に頭に残ります。本州の端にある赤間関市で生活する徹と相沢の不思議な関係から、逃れられない血族の血というものが流れていくのが鳥肌の立つほど鮮明な赤い血液として見えるようでした。気味悪く這いずり回る蟹、燃える聖堂、登場する全ての人々が滅びへと誘われていく様子が針のように全身に降りかかってくるようでした。生活する土地と血縁は逃れられるものではない恐ろしさをつくづく感じました。体の中の血が沸騰するような感覚に陥ります。
2014/09/01
梟をめぐる読書
安徳天皇入水の地である下関市をバックグラウンドに、マクロな世界史の動きと織り重なるようにして地方の人々のミクロな営みが記述されていく。戦後日本社会のあらゆるテーマや矛盾を包括し、ときにはマジック・リアリズム小説のような交霊的なヴィジョンも交えながら、そのすべてを過不足なく描ききってしまう著者の筆力に脱帽。テロを超えて、あるいは〝神〟を超えて人々に支配を及ぼす「力」とは何か。現代文学が未解決のまま踏み越えていった諸問題(あるいは近代文学という「巨人」)に、著者はひとり立ち向かおうとしているのかもしれない。
2013/11/17
ハチアカデミー
本書は不敬小説ではない。天皇家の「嘘」を暴くことが本書の主眼ではない。神をも含めた壮大な父殺しの物語である。世界の「無意味」(≒虚無!)と向き合いつつ、血縁という「意味」に縛られる生活を描く。そこで見えてくるのは、天皇制に象徴される戦後の社会構造の限界である。それを真っ正面から作品化し、平成史として提示する。同時代作家の小説を読む醍醐味が味わえる傑作である。戦後の終わりを告げる儀式であるかのような、小さな村の祭りに全てがぶち込まれる壮絶なラストが強烈。これまでの田中慎弥作品全てを飲み込む作品である。
2013/11/04
にこ
読み終えて真っ赤な表紙を見ると蟹があふれてきそうな錯覚を起こさせる。蟹はしばらくいいな。。燃える前のサビエル記念聖堂や下関市の街並みの雰囲気、豪華絢爛な先帝祭など馴染み深い題材だっただけにとても読みやすかったのだけれど、どこにも救いがなく、最後は苦しくなった。
2014/02/05
感想・レビューをもっと見る