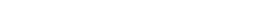1973年のピンボール (講談社文庫 む 6-28)
1973年のピンボール (講談社文庫 む 6-28) / 感想・レビュー
ヴェネツィア
登場人物同士の関係性がきわめて希薄な物語だった。「僕」と「鼠」とが、ほぼ交互に描かれるが、ほんのわずかな回想シーンで時間を共有するだけで、それ以外には全く交点を持っていない。また、「僕」が一緒に暮らしていた双子には名前がないし、208,209などと記号化してしまっている。「鼠」の相手にもやはり名前はなく、単に「彼女」と呼ばれるだけだ。表題にもとられたピンボールの無機質感や空虚感もあいまって、物語全体を一種のニヒリズムが覆うかのようだ。
2012/06/04
ehirano1
「入口と出口(≒双子、鼠)」「喪失との決別(≒直子)」「リプレイ(≒ピンボール)」を巧過ぎるくらいに繋げたある種独特の雰囲気を楽しむ読書となりました。尚、「風の歌を聴け」や「ノルウェイの森」を読んでからのほうがより味わいを楽しめると思いました。
2024/07/22
zero1
すべては過ぎ去る。貯水池の配電盤や双子の姉妹。入り口と出口。それでもスペイン語講師のようにピンボールに執着する人たちがいる。メカニカルなピンボールには、今のゲームにはない味がある。TILT(揺らすと機械が止まる反則)がその代表。鼠は街を出るが、その後は「羊をめぐる冒険」で分かる。何度目かの再読だが、この作品が芥川賞を落選するのは妥当な判断。散漫だし、多くの選考委員から賞賛を得られる作品ではない。だが、委員たちが求めるものがなかったからと言って価値がないわけではない。小説とはそういうものだ。
2018/11/05
tokko
短い挿話がいくつも重ねられて一つの物語へと導かれていく。まるで実験的な映画を観ているような雰囲気に引き込まれた。「配電盤」の死、「スペースシップ」との再会、「双子の姉妹」との別れ…。「僕」にとって「スペースシップ」との邂逅は、次のステップへ進むための手続きなのか。
2011/07/03
夢追人009
村上春樹氏の初期3部作の2冊目。冒頭に金星生まれと土星生まれが出て来るのは前作の架空作家と併せてこの物語がパラレル・ワールド(並行世界)の話だからなのでしょうね。白い大きな犬・アビシニア猫の動物達、208と209の双子姉妹は僕にとってそれぞれに愛する直子の死の悲しみを乗り越えさせる癒しになったでしょう。鼠は我慢せずに彼女の家に行ったらもう少し長続きしたかも知れませんが所詮は時間の問題だったでしょうね。僕と3フリッパーのスペースシップ、鼠とジェイ、僕と双子の別れ。月並みですが「さよならだけが人生だ」ですね。
2018/10/03
感想・レビューをもっと見る