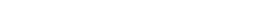晩年様式集 (講談社文庫 お 2-22)
晩年様式集 (講談社文庫 お 2-22) / 感想・レビュー
ASnowyHeron
自分は初めてこの作家の作品を読んだせいもあるのだろうが、作者を模した主人公やいろいろな話がこんがらがって、なにがなんだがわからなかった。
2017/03/07
ちぇけら
残された時間はそう長くないのだという感覚。さんざん想定されていた「想定外」の事故が起きてもなお原子力発電所は動き続けている。「私らは侮辱のなかに生きています。」過去を描くことは未来を語ることと同義だ。日本は「3・11」を境に大きく変わってしまったが、「3・11」の前から、それは始まっていたのだ。「3・11」は引き金にすぎない。地盤が揺らぎ、銃は放たれたのだ。そこに自らの「小説」と「人生」とが重なり、オーケストラのような重奏感が生まれる。この光の輪郭は、「希望」なのだろうか。ぼくは、そっと目を閉じて祈った。
2020/08/29
タイコウチ
震災後に書かれた「最後の小説」で、ノーベル賞受賞後にもう書かないといってから『取り替え子』で始まった長江古義人シリーズの締めくくりでもある。これまでの作品の様々なモチーフが再訪されるとともに、自分が作品の中で一方的に描いてきた妹、妻、娘らから反論・反撃される(という自分の姿を自虐的ユーモアに包んで描いている)という多声的・多層的な構成。実は『取り替え子』に続く『憂い顔の童子』と『さようなら、私の本よ!』の2冊は文庫が入手できず未読なのだが、大江健三郎という作家の最後の小説として納得のいく見事な作品だった。
2023/05/31
井蛙
大江の小説には《溺死しかけたところを母親に救われる》という原体験が何度も描かれるけど、実は彼を救ったのは母親じゃなくて妹だったっていう結構重要なことかさらっと書かれていたりする。その点も含めて、この作品では初めて著者が彼の書いてきた人や物事から正面きっての批判を浴びせられている。それらにはすでに死んだ人間を語りうるのは生きている人間だけであって、その特権的な地位に与っていた著者の生命がもはや僅かしかないという焦りもあるだろう。その中で詩人に憧れ続けた著者は祈りにも似た一連の詩で掉尾を飾るのだが、それより→
2019/09/14
belier
大江健三郎「最後の小説」。2011年末から2013年夏にかけて書かれただけに震災、原発事故、自身の老いが反映し、これまでの作品世界を集大成する作品のはずだが、不安感と自己批判に満ちた重苦しい展開。しかし、ラストはやや強引に明るい方向へ転じ、震災前の2006年末に書いたという長い詩で締めくくられる。その中の「否定性の確立とは、なまなかの希望に対してはもとより、いかなる絶望にも同調せぬことだ・・・」という一節が自分には印象的。決めの文は「私は生き直すことができない。しかし私らは生き直すことができる。」
2022/05/04
感想・レビューをもっと見る