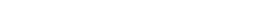ノストラダムスと王妃(下) (集英社文庫)
ノストラダムスと王妃(下) (集英社文庫) / 感想・レビュー
エドワード
ミシェル・ド・ノストラダムスの名は、大天使ミカエルとノートルダムこと聖母マリアに由来する。改宗ユダヤ人の彼はこの名でキリスト教社会へ溶け込んだ。ペテン師でも嘘つきでも無い思慮深い人物として描かれる。彼の予言の真相「1559年7月、国王アンリ二世崩御」は的中した。王妃マルゴの母、カトリーヌは情容赦無い冷血女として描かれることが多いが、この作品では、必死に生きる一人の女性である。ヴァロア朝からブルボン朝へ移るフランスは、殺さなければ殺される、まさに戦国時代だった。アルベルトとビラーグの二人のしもべが痛快だ。
2014/03/03
ごんちゃん
後半戦、権力闘争激化でピンチにつぐピンチ。カトリーヌ王妃、どーして次期国王である自分の息子をちゃんとグリップしとかんかった?というか、最初から長男が長生きしそうにない状況で、次の王位継承権を持つ息子達がいれば、粗略に扱われないように思うけど。だから逆に疎まれたのかね?史実的にはどーなんだろう?面白かったけど、ちょっと引っかかるな。ノストラダムス先生は、活躍したようなしなかったような・・。
2017/08/07
さくら
アルベルトに続きビラーグもカトリーヌから離れ、一時どうなる事かと。 やきもきされ、なかなか面白かったです。 策士で野心もあったノストラダムスが、預言ではなく、最後は家族の幸せだけを願う。その穏やかさに心和ませた。 *タイトル変更前⇒「預言者ノストラダムス」
2012/07/17
HoneyBear
この小説は凄い。カトリーヌ・ド・メディシスとノストラダムスの人物や感情までが活き活きと描かれる。宮廷の様子なども面白い。権謀術数の渦巻く16世紀前半のフランス(ユグノー戦争勃発前)で、いかにして孤立無援の母后が、数々の危機を乗り越えて権力を得ていく様子が面白く、途中で止められなくなった。どこからこの構想力は来るのだろうか。
うたまる
「恨みます、ノストラダムス。そなたさえいなければ、そなたさえ預言をしなければ、私は、何も知らずにすんだ。国王殺しにも、子供殺しにもならずにすんだものを」……面白かった。王位を狙うブルボン家とギュイーズ家を牽制し、また頑迷なカトリックと非妥協的なプロテスタンのバランスを取るには、このような方法しか無かったのかもしれない。後の世のカトリーヌとノストラダムスの悪名は、何をしても、しなくても、喧伝される運命にあったのだろう。
2014/11/24
感想・レビューをもっと見る