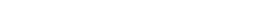母性のディストピア
母性のディストピア / 感想・レビュー
みのくま
本書はとても精巧に作り上げられた砂上の楼閣だ。宮崎駿、富野由悠季、押井守らの作品を批評的に解釈し、著者の持つ独自の世界観を「補強・補完」している。つまり本書は「作品批評」ではなく、宇野常寛の見えている世界を表現するためだけに戦後の日本アニメが使われているのだ。彼の持つ世界観は、夫=子を支配しようとする母性を嫌悪し、母からの承認で父性を回復する男を嫌悪する。安易な物語(家族、国家、恋愛、成熟)を拒否し、それに付随する自意識を嫌悪する。世界の全ては情報の集積として処理し、興味や面白さ(=市場)で行動すべし。続
2017/11/25
姉勤
宮崎駿、富野由悠季、押井学。いまや世界に通じる著名なアニメーション作家である彼らの作品群から、戦後表立って語られることを忌んで来た「政治」や「戦争」そして「独立」についてアニメという形で世に出した、彼らの創り出すドラマや物語に現実を反映させ、もしくは回避させていた団塊ジュニアとその周辺の世代が、永いモラトリアムの中で歳をとってしまった事。そして彼らを魅了した、時代を洞察し映像化した才能、「映像の時代」に開花した事が、逆に現在の「情報の時代」に人心が仮託できる映像を世に出せなくなっていると指摘する。
2019/09/30
梟をめぐる読書
宮崎駿、富野由悠季、押井守。戦後アニメの巨匠として知られる監督たちの経歴を辿り直すことによって、日本という国家の欺瞞と近代的「成熟」の不可能性を明らかにする。現時点における著者の集大成というべき、包括的な大著。永久に「子」を母胎に留め置くことによって「父」としての成熟を不可能にする、戦後日本の想像力を支配する呪いのような力学――作者はそれを「母性のディストピア」と呼ぶ。そこから導き出されるのは、もはや凡庸なアニメ論ではありえない。「母」に挑んでは敗北を繰り返す、戦後アニメを支えた男たちの壮大な「偽史」だ。
2018/02/02
しゅん
現実的には役立たずな理想を「あえて」肯定し、「あえて」偽善を引き受ける点で戦後民主主義と保守思想は同根であり、そうしたアイロニーは女性=「母」を犠牲にすることで保たれる。その日本的システムの分析として宮崎駿・富野由悠季・押尾守を中心とした日本アニメを扱い、更新の可能性を探る。本書の見立ては大凡このようになっている。「母」のメタファーは本書では家族構造のカナメと情報社会の広がりの双方に跨るが、どちらも構造の基盤である点は共通する。そうなると必要とされるのは構造分析だが、果たして本書で為されているのだろうか。
2023/07/23
Fancy Koh(旧SMOKE)
戦後日本の欺瞞をアニメを通じて論じた大作。面白い。アニメという市場に影響されやすい分野だからこそ、その時々の大衆のメンタリティがもろに影響される。ロボットアニメの終焉は、戦後民主主義の終焉であるし、その後、「ヤマト」「ガンダム」「エヴァンゲリオン」以降世間を揺るがすエポック的なロボットアニメがないのは、まさに筆者のいう通り「失われた二十年」のもがきそのものなのだろう。アニメ好きではなくても、ヒステリックなイデオロギー論争に嫌気がさしている人は面白いと思う。
2017/11/25
感想・レビューをもっと見る