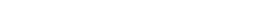文鳥・夢十夜 (新潮文庫)
文鳥・夢十夜 (新潮文庫) / 感想・レビュー
ヴェネツィア
今回は「文鳥」のみの感想。漱石41歳の作品である。この頃、漱石は『虞美人草』の執筆をはじめており(作中で執筆中の小説はこれかと思われる)、いよいよ職業作家になろうとしていた。作中には「赤い鳥」の鈴木三重吉や小宮豊隆も登場し、漱石の周囲に一種の文学サークルのようなものができつつあったことをもうかがわせる。そうした経緯で飼育することになった文鳥だが、漱石の文鳥に対する観察の細やかさとともに、文鳥の世話を怠り、挙句に死なせてしまったばかりか、その責任を転嫁する自分自身を見つめる冷徹な目がそこにはあるようだ。
2017/01/10
まさにい
夢十夜を久しぶりに読もうと思ったのだが、小品の『思い出す事など』の方が今回は印象に残った。漱石が修善寺で、生死の境を彷徨った時の漱石自身が思い出す事を綴った随筆ともいうべきもの。血を吐いた時のこと、その後のことなどが素直な気持ちで書かれている。また、この『思い出す事など』は、33の小文から、成り立っているのだが、それぞれの小文の最後に漢詩か短歌がうたわれている。これが、枯れていていい味を出している。夢十夜よりこっちの方が印象に残るのは僕が齢を重ねたせいなのかなぁ。ちょっと寂しい秋の読書になった。
2016/10/16
Major
第十一夜:こんな夢を見た。雪の日だった。豊かな長い黒髪の女が突然亡くなった。釘打ちの鈍音が波紋のように幾重にも輪を描いて、鉛色の空へと響き染みていった。僕はようやく旅立てると思った。その日も小雪がちらついていた。雪はいつでも思い出を運ぶ。雪はその白さとともに、幾分かのロマンティック、センチメンタルやメランコリーをその身に纏いながら、物語にして地上に舞い降りてくるのだ。北へ北へと闇を駆け抜ける列車はその響きだけを残していく。故郷が、友が、そして青春時代が、進みゆく列車と共に離れ去っていく。。
2020/05/11
こーた
日常のなかに、不図あらわれる非日常。縁側の鳥かごから療養先の天井まで、異世界の口はどこにでも開いていて、だれでも容易く行き来することができる。意識に無意識が混ざりあい、彼岸と此岸を往来し、夢の世界へ迷いこむ。小説なのか随筆なのか、あるいはその中間なのか。デッサンのようだが纏りがあって、怪談のようで神話のようで、作家は思索し随想もする。自在な語りは落語のようで、この小品たちこそが、異界へのみちびきそのものでもある。漱石先生が見る夢、魅せる夢。こんな夢ならばずっと見ていたい。【酉年の漱石忌に】
2017/12/09
ちくわ
【文鳥】ペットを飼うにはあまりに無責任な漱石に絶句する。自分のプロフィール画像は昔飼っていたハツカネズミで、ニックネームはその名前である。全く懐かなかったが、日々愛情を持って世話をした。無論一方的な愛情であり、ちくわがどう思っていたかは分からない。しかし平均寿命約2年に対して3年半と長生きした。野生で生きる事は非常に大変だ。その点ペットは無償で食料や水、安全な棲み処を与えられる。代わりに自由を失う。選択肢は無い。我々は選択肢を持てる事の倖せとその責任をもう少し自覚するべき存在だと本作は教えてくれたのかな?
2024/05/13
感想・レビューをもっと見る