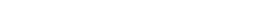忘却の河 (新潮文庫)
忘却の河 (新潮文庫) / 感想・レビュー
ヴェネツィア
1960年代の小説とはこうであったのかと、小説としての「時代」を強く感じさせる作品。また「語り」に工夫の凝らされた小説である。すなわち冒頭の第1章「忘却の河」と最終章の「賽の河原」は「私」の、そして第4章「夢の通い路」は、妻の一人称語りであり、他の章ではそれぞれ中心となる人物は異なるが客観体で語られる。私と妻には、それぞれ過去が払拭できないものとして揺曳する。二人の娘たちにとっても近過去はまた重い。最終章でわずかに希望の曙光は見えるが、自己の人生が失敗であったかのように悔恨される暗鬱な小説である。
2018/08/31
遥かなる想い
各章が語り手を変え、文体を変え、そして ゆるく 繋がっていく。過去と現代を巧みに 交錯させながら、物語は繋がる..それにしても 著者の描くヒロインは清冽で慎ましげである。 同じ時間を過ごした家族の別々な視点.. ドラマ的だが、ドラマでは描ききれない心の 動きを巧みに描く、昭和の家族の物語だった。
2017/02/05
ナマアタタカイカタタタキキ
我々は、各々で違う様相の地獄の中で生きている、といえるのかもしれない。穏やかな日常、陽だまりの風景の中にだって業火は存在しうるのだから。その炎から逃れるために、魂は故郷を求めて彷徨い続ける。生きている限り永遠に。生とは、単にその放浪の最中に力尽きてしまうだけのものなのだろうか?──何気に再読だった。文学的ピカルディ終止とでも称したくなるような幕切れ。語り手ごとの書き分けも妙を得ていて、構成も見事。著者にとって普遍的なテーマである“愛と孤独”が、『草の花』の澄みきった空気感とは別の形で表現されている。良き。
2021/06/22
KEI
7つの章が父親、長女、次女、妻、長女を思う既婚の男らの独白の形で繋がる短編連作短編集。誰もが抱えている罪の自覚、死への思い 、愛することへの希求。家族である4人は家族であるが故に、より孤独に満ちている。生きていく中で救いはあるのか?と静かな文章が問いかけてくる。時折グサリと心に響いて読むのが辛い。 でも、人は生きていかねばならない。7章の父親の気づきや長女が父親に「私はそういうお父さんが好きよ」との生への肯定に救われる。人は誰かに認められ、愛されて前へ進む事が出来るのだと感じた。
2018/03/27
市太郎
感想をどのように記そうかと・・・。というのも光明が差し込んだはずの第7章で途端にこの小説がわからなくなったからだ。この最終章に行き着くまでの永い孤独に関しては著者の「愛の試み」を事前に読んでいた為、読解の助けとなり、孤独と愛について考える上で自らの罪に苦しみ、忘却しようとした記憶と決して消える事のない過去から続く現実が自身の胸に残り、救われるはずがないと思い込んで読んでいた為に起った戸惑いか。どの様な形の「答え」であるにしても第1章から愛の兆しはあったのだろう。「草の花」も読んでみたいと思いました。
2018/04/08
感想・レビューをもっと見る