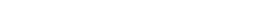死海のほとり (新潮文庫)
死海のほとり (新潮文庫) / 感想・レビュー
ヴェネツィア
小説は3つの時間と空間とから構成される。現代のパレスチナでの私と戸田、第2次大戦中の上智大学での私たちとねずみ(コバルスキ)、そして2000年前のパレスチナでのイエスとその周辺の人々。これらの3つの時空を貫流するもの、そして中心に位置するものは実は1つだ―すなわちイエスに他ならない。ここでの問いかけも基本的には『沈黙』と同じだ。ただ、『沈黙』が、神への問いかけだったのに対して、今回はイエスへのそれだ。それにしても、ここで描かれるイエスはなんと無力なのだろう。また、逆説的なのだが、だからこそイエスなのだ。
2014/06/22
遥かなる想い
戦時の弾圧の中で棄教に悩む主人公がエルサレムを訪れ、真実のイエスを求め、死海のほとりをさまよう物語。私にはなじみの薄いイエスの軌跡が新鮮に伝わってきた記憶がある。あえて無力なイエスを描くことにより、 宗教の根本を描こうとしたのだろうか・・正直難しい本であった。
優希
イエスの足跡を辿る「巡礼」とイエスの時代を描いた「群像」が見事にフーガを奏で、イエスの姿の本質が追求されているように思えました。ここで描かれるイエスは、どこまでも哀れで弱いですが、それこそが真実のイエスであり、人々の隣人となるべきことができた姿なのかもしれません。信仰につまづいた主人公と共に見ていくイエスは、「救い主」ではなく「傍に寄り添う」イエスそのものだと感じました。それこそが周作先生の捉えるイエス像そのものなのでしょうね。
2018/03/27
Gotoran
死海の畔を舞台に、戦時下の弾圧の中で信仰に躓きキリストを棄てようとした小説家の”私”が、イエスの足跡を求めてイスラエルを巡礼する「現代の話」とイエス・キリストが伝道のためにパレスチナを旅する「過去の話」が交互に展開していく。無力で弟子から見捨てられ惨めに磔にされたイエス。信仰に躓いたがゆえに求め探し当てたイエスの姿は福音書での力ある救世主ではなく、弱者の傍にただ寄り添い共に苦しむことしかできない同伴者でしかなかった。著者の信者としての葛藤と悟りをそのまま描写しているような作品で読み応え十分だった。
2020/05/13
GAKU
小説家の「私」がエルサレムを訪ね、在住の友人で聖書学者の戸田とイエスの足跡を旅する『巡礼』と、ゴルゴダの丘でイエスが磔にされるまでの『群像』の二つが交錯する物語。『巡礼』ではイエスから逃れ、信仰を棄てようとしてもそうする事が出来ない「私」が描かれている。『群像』では神の子としてではなく、悩み苦しむ一人の人間としての「イエス」が描かれている。この作品でも遠藤周作氏は信仰とは?愛とは?そしてイエスとは?を読者に問いかけている。そして氏の作品を読む度にいつも私は何も答える事が出来ない。⇒
2016/08/17
感想・レビューをもっと見る