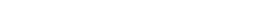荒野のおおかみ (新潮文庫)
荒野のおおかみ (新潮文庫) / 感想・レビュー
ヴェネツィア
これまでに読んだヘッセとはかなり雰囲気を異にする小説作法だ。本書は第1次大戦後のドイツを背景に書かれており、作家自身の強い危機感が「疎外」という形で投影されているように思われる。ヒトラーの台頭はまだだが、新たな戦争へと向かっていきそうな気配が感じられる。ヘッセにとっては、一層に痛切だっただろう。物語の後半は迷宮世界を描き、さながらヘッセ版『ファウスト』といった趣きだ。こうした幻想の形をとることで、またアウトサイダーたる「荒野のおおかみ」を身に纏うことで、作家は自分自身にも秘めてきた自己を語ったのだろう。
2015/09/12
遥かなる想い
1925年に書かれたこの本はヘッセ50歳の 心境が反映された本らしい。ハリー・ハラーと いう人物を通して垣間見られるヘッセの苦悩は 時代の反映なのだろうか。 美少女ヘルミーネとの出会い、マリアへの恋が 心の救済となるのか.. ひどく読みにくい内面描写が エミールの登場とともに晴れやかに変わって いくのも興味深い。 現実と幻想が入り混じり、精神が解放されて いく描写は正直ついていけなかったが、 時代の雰囲気は感じられた気がする、そんな本 だった。
2016/04/10
ケイ
再読。荒野のおおかみと言う表現からは、孤高で強く美しいイメージがまず浮かぶ。しかし、孤独がツラければ、そして周りに溶け込めない自分を持て余しやり切れないのなら、孤独は壮絶なものかもしれない。その上、オオカミはハンターに狙われ、追われる存在だ。それを克服するにどうすればいいのか、どうしたら生きやすくなるのか。ゲーテやモーツァルトなど、精神の対話を通じて見えてくる精神の安らかさ。万人への処方ではなくとも、彼が自分なりの光を見出していこうとしたことに希望を感じる。
2016/12/20
まふ
50歳のハリーは自縛的知識過多の己が命の意味を見失い苦しむ。ゲーテ、モーツアルトの世界との現実の世界のギャップ、この苦悩の前半の叙述が重苦しいがきわめて面白い。哲学的思弁的な理念型だけではカバーできない現実世界の巨大さ多様さ。「単純であることの奥深さ」をヘルミーネとの邂逅によって初めて「体感」し、本当の「生」の意味に目覚める…。「ヘッセ節(?)」に久しぶりに酔った。ワグナー派とブラームス派との論争も笑い飛ばし、読者に「まあそんなものだろう」と思わせる著者の筆は今更ながら「冴えてい る」と思う。G1000。
2023/05/22
こーた
狂気に包まれてゆく社会に背を向け、自身をとことんまで見つめようと奮闘する"荒野のおおかみ"ハリー。性の享楽と愛の陶酔に充ちた地下の魔術劇場では、鏡のなかに醜い自分を見出し、敬愛するゲーテやモーツァルトとの対話によって自己の浅はかさを突きつけられる。それは夢か幻か。悪夢なのか悟りなのか。自身に潜む人間的な部分とおおかみ的な部分に引き裂かれながらも、自分自身の深部へと分け入っていくさまは、苦しくも怖ろしい。だが周囲に同調して生きていくよりは、ずっといい。わたしも荒野のおおかみのように生きられたら、と強く思う。
2018/01/15
感想・レビューをもっと見る