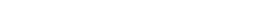年の残り (文春文庫 ま 2-1)
年の残り (文春文庫 ま 2-1) / 感想・レビュー
ヴェネツィア
表題作は、第59回(1968年上半期)芥川賞受賞作。文体といい、主題内容といい、なんと老成した小説だろう。新進作家の登龍門たる芥川賞におよそ似つかわしくない作品だ。悪いと言っているのではない。むしろ出来過ぎなのだ。これは谷崎賞にこそ相応しいくらいだ。もっとも、受賞時に丸谷は43歳だから、かなり遅い受賞だ。しかも、既に永川玲二たちと『ユリシーズ』の翻訳も出版していた。それにしても、老年であることへの想像力は恐るべきものだ。そして、読後には冒頭のエピグラフ「かぞふれば年の残りも…」が回帰してくるのである。
2015/10/29
遥かなる想い
第59回(1968年)芥川賞。 69歳の老院長 上原庸の過去を巡る 心の動きを、 丸谷才一が闊達な文体で描いた作品である。 老境にある時、過去に人は何を見るのだろうか? 上原の友人、桜林堂主人多比良の 奇妙な生き方が 印象に残る作品のだった。
2017/08/23
kaizen@名古屋de朝活読書会
芥川賞】家族って何だろう。暗すぎて考えたくなくなりそう。暗けりゃ文学だというのでは嫌だ。息子が死んでしまうあたりの描写がおざなりなのは何故なんだろう。納得感がない。
2014/02/20
metoo
69歳医師上原が、高校1年の正也に40年前に描いた水彩画を見せるところから始まり、正也の日記で終わる。絵の上手い同級生が自殺したことで、心の襞のひとつひとつがざわざわと騒ぎ出す。同級生の優秀な息子、女と多数交わるのを生き甲斐とする同級生など、他人を羨望する心を律し、69歳の医師の心情を、過去から現在を軽やかに行き来し、人生を俯瞰しつつ巧みに表す。この歳になってみて響く内容だが、著者43歳の作品と知り驚く。最後の正也の後日談的な日記が特異であり試作的かなと、そこに若さを感じた。
2017/05/29
hit4papa
老境に入った男たちの生と性に対する悲哀が描かれたタイトル作は、時制を前後させた濃密なお話に仕立てられています。世間的な成功をつかみながらも、これから人生に諦めがつくかつかないかの境界で戸惑う瞬間ということになるでしょうか。文章に取り消し線を用いるといった手法は、行間をチラ見せさせられているような不思議な感覚を味わいます。主婦のよろめき「川のない街で」、疎んじていた旧友との邂逅「男ざかり」、ある男の思想史「思想と無思想の間」、ともにページ数の割に結末の予想がつかないほどに密度が高い作品です。【芥川賞】
2017/12/13
感想・レビューをもっと見る